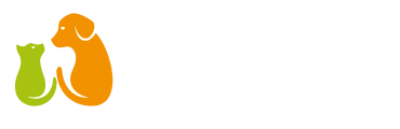ペットビジネスのマーケティング基礎知識

日本のペット市場を読み解く
日本のペット業界は着実に成長を続けています。その背景には、社会の変化に伴う飼い主の意識の変化があり、単なる「飼育対象」ではなく「家族の一員」としての認識が広まったことが大きく影響しています。ペットビジネスに関わる上で、市場の現状や動向、飼い主ニーズの変化を正確に理解することは不可欠です。
本記事では、近年の信頼性の高いデータや動向をもとに、現在のペット市場の実態を整理し、今後の事業戦略に役立つマーケティングの視点をお伝えします。
ペット飼育の現状と課題:減少傾向と高齢化
近年、日本のペット飼育頭数は減少傾向にあります。2023年の一般社団法人ペットフード協会の調査※1によると、犬・猫合わせた飼育頭数は過去と比べ減少しつつあります。
ただし、最新データでは犬の飼育頭数の下げ幅は縮小しており、猫の飼育頭数は横ばいの傾向を示しています。新規飼育頭数や飼育意向率についても、犬・猫ともに前年とほぼ同水準で推移しています。
加えて、ペットの高齢化も進んでおり、平均寿命は犬で14歳前後、猫で15歳以上とされています。これにより、飼い主がペットの介護や医療に関心を寄せる機会も増え、健康維持や予防ケアへの意識が一層高まっています。
市場規模の推移と成長要因
ペットの飼育頭数が減少する一方で、市場規模は拡大傾向を維持しています。矢野経済研究所※2によれば、2023年度のペット関連市場は約1.86兆円に達し、2024年度には約1.90兆円に拡大すると見込まれています。
この成長を支えているのが、「ペットの家族化」による一匹あたりへの支出増です。ペットフードや動物病院での治療費だけでなく、サプリメントやトリミング、保険、プレミアムフードといった付加価値サービスの利用が増加しています。特に健康意識の高まりに伴い、単なる消費ではなく“長く健やかに暮らす”ための選択が重視されています。
健康志向の高まりと製品トレンド

ペットを家族と位置づける飼い主の間で、「健康志向」はますます重要な購買基準となっています。以下のような製品やサービスが注目されています。
- ヘルスケア商品:免疫力向上や関節ケアを目的としたサプリメント、栄養補助食品など
- プレミアムフード:グレインフリー、オーガニック、アレルギー対応の高品質フード
- ペット保険:予防から治療までカバーする保険加入率も年々上昇傾向※3
ペット飼い主の防災意識と準備の現状

災害大国の日本において、ペットとの暮らしには災害時の備えも無視できません。実際の調査では、犬飼育者の3~4割が「ペットフードの備蓄」「キャリーバッグの用意」「トイレ用品の準備」などを行っている一方で、20代の実施率は全体平均よりも低い傾向があります。
猫飼育者ではやや高い備蓄率がみられるものの、全体として防災対策の徹底には至っていません。また、「同行避難」と「同伴避難」の違いを正しく理解しているのは6割程度、実際に最寄りの避難所を把握している人は2割未満という課題も明らかになっています。
こうした背景を踏まえ、ペット関連事業者へのヒントとして以下のようなものが考えられます。
- 商品やサービスに「防災対応」の付加価値を加える(例:非常用フードキット、防災バッグ付きケージなど)
- 防災知識を啓発するコンテンツの提供(例:ブログやSNSでの備えチェックリストの公開)
- 店頭やECでの訴求に「防災」の切り口を設け、飼い主の不安に応える安心材料として打ち出す
特にまだまだ意識の低い若年層への情報発信では、動画やSNSを通じた分かりやすく実用的なアプローチが効果的かつ啓発にもつながると考えます。災害時にもペットと一緒に安心して避難できる社会づくりに、事業者として貢献する姿勢が、飼い主の信頼の醸成につながり、ひいてはブランドへのファン化も望めるのではないでしょうか。
ペットがもたらす感情的な効用
「ペットビジネス」というと、つい商品やマーケティング手法の良し悪しにとらわれてしまいがちですが、ペットを飼うことによる効果として、「癒し」「安心」「孤独感の軽減」などの感情面の効用が大きく認識されています。そのほかにも通院回数の減少や交友関係の拡大などもペットを飼うことの効果です。
こうした感情を動かすさまざまなことが、ペット飼育意向の原動力となっていることから、商品やサービス開発においても“共感”や“感情価値”をないがしろにせず、むしろ「軸」として据える視点が重要です。
飼い主心理の理解がマーケティングのカギ

飼い主は「情報に敏感」で「間違えない選択をしたい」と感じています。したがって、マーケティングの視点では、単に製品の機能を伝えるだけでなく、
- なぜこの商品が“うちの子”に合うのか
- どのように選べば安心か
- 誰が推奨しているのか(専門家、愛用者の声)
といった“納得感”を与える情報提供が重視されます。また、SNSを通じた体験共有や口コミの影響力も大きく、商品そのものに「ストーリー」があることがブランド選定に直結するケースも増えています。
今、ペットビジネスの戦略に必要な視点
ペットビジネスで成功するためには、「健康・安心・共感」を軸としたマーケティング戦略が求められます。以下のポイントを意識すると良いでしょう:
- データと感情の両面から飼い主ニーズを把握する
- 一過性ではない“継続性”を前提とした商品開発
- 信頼を構築するための情報発信と専門性の可視化
また、高齢化・単身世帯の増加など日本社会の構造変化を踏まえ、ライフスタイルに寄り添ったサービス(例:訪問トリミング、ペット用見守りカメラなど)にもチャンスがあるのではないでしょうか。
まとめ
日本のペット市場は、量的拡大よりも「質的深化」のフェーズに入っています。ペットの家族化、飼い主の健康志向、そして安心・信頼を重視する消費行動が、今後のペットビジネスの中核を担うテーマです。
単なる商品提供ではなく、「飼い主の想いに寄り添う姿勢」こそが、これからの時代に選ばれる企業・ブランドの共通点となるでしょう。
<出典>
参照:一般社団法人ペットフード協会 「令和6年(2024年)全国犬猫飼育実態調査 調査結果の要約」
https://petfood.or.jp/pdf/data/2024/2.pdf
※1 一般社団法人ペットフード協会 「令和6年(2024年)全国犬猫飼育実態調査」
https://petfood.or.jp/data-chart/
※2 矢野経済研究所「ペットビジネスに関する調査を実施(2024年)」
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3568
※3 アニコムグループ「中期経営計画2025-2027」
https://www.anicom.co.jp/ir/pdf/20250509.pdf
ペット商品に信頼感を与える
獣医師監修サービスを提供しています
ペット商品に信頼感を与える
獣医師監修サービスを
行なっております