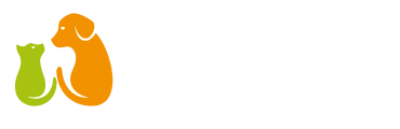これからペット事業を始めたい!成功する立ち上げのための5つのステップ

ペット市場は右肩上がりの成長を続けており、2023年度には約1.86兆円、2024年度には約1.90兆円に達する見通し※です。人間と同様に「家族」としてペットが迎えられるようになり、D2C(Direct to Consumer)やペット向けのサブスクリプションサービスなど、新たなビジネスモデルも急増しています。一方で、立ち上げの段階で「方向性が定まらない」「差別化ができず売れない」といった声も少なくありません。
※出典:矢野経済研究所「ペットビジネスマーケットに関する調査2024」
本記事では、これからペット事業を立ち上げる方に向けて、成功の確率を高めるための5つのステップを、事例や注意点も交えて詳しく解説します。記事の後半では、よくある失敗パターンとその回避方法についても触れています。
ステップ1:ニーズを捉える市場調査とターゲット設定

最初に行うべきは、“誰に何を届けるか”を明確にすることです。ペットと一口に言っても、犬・猫・小動物・爬虫類・鳥など多種多様ですし、飼育スタイルや飼い主の価値観もさまざまです。最近では、「高齢犬向けの介護用品」や「猫の腎臓ケアフード」など、よりパーソナライズされた商品が人気を集めています。
市場調査をする際には、次のような観点が参考になります:
- 対象とするペットの種類(例:犬特化、猫と小動物など)
- 年齢やライフステージに応じたニーズ(シニア犬、子猫、成長期のうさぎなど)
- 飼い主の属性(年齢層、生活スタイル、居住地域など)
- 既存市場の商品傾向とトレンドの変化
このように細分化した視点でターゲットを定めることで、その後の商品設計やプロモーション戦略に大きな差が出ます。
ステップ2:世界観を明確にするブランド設計

ターゲットが明確になったら、次はブランドづくりです。ペットは家族の一員であるため、飼い主は商品に対して非常に強いこだわりを持っています。商品の良さだけでなく、その背景にある「世界観」や「共感できるストーリー」も購買の決め手になります。
ブランド設計においては、以下の3点を明確にしましょう:
- ブランドの使命(例:「すべてのペットにやさしさと安心を」)
- コンセプト(例:「無添加・国産・サステナブルなペットライフ」)
- ビジュアルトーン(ロゴやパッケージ、SNS投稿などのデザイン一貫性)
ブランドは「売るための道具」ではなく、「信頼を得るための基盤」として考えましょう。
ステップ3:ニーズに応える商品・サービス開発

いよいよ具体的な商品やサービスの設計段階に入ります。
主な商品・サービスのカテゴリとしては以下となります。
- フード・おやつなどの消耗品
- ハーネス、おもちゃ、ケージなどのグッズ類
- オンラインしつけ講座や飼育相談などの無形サービス
- 定期便・サブスクリプションモデル
このフェーズでは、「どうやって差別化するか」がカギとなります。
- どんな課題を解決できるか?(例:アレルギー対策、肥満防止)
- 他社との違いは何か?(例:獣医師監修、素材へのこだわり)
- 顧客の声をどのように取り入れるか?(例:レビュー、テスト販売)
特にペットは命に関わる存在なので、「安全性」や「信頼性」はとても重要な評価軸です。企画段階から専門家の意見を取り入れることで、商品化後のトラブルやクレームを未然に防ぐこともできます。
ステップ4:売れる仕組みをつくるチャネルと販促戦略

商品やサービスが決まったら、次に考えるべきは「どうやって売るか」です。販売チャネルと販促施策の設計も、ペット事業では大きな成功要因となります。
- オンライン:ECサイト、モール出店、SNS販売など
- オフライン:ペットショップ、動物病院、イベント出展など
- ハイブリッド:リアルとデジタルの連動(例:ポップアップ+LINE公式)
販売チャネルに応じて、プロモーション施策も変わります。PRタイミングやインフルエンサー施策、口コミ生成、飼い主のレビュー体験の設計など、導線づくりの工夫が必要です。
ステップ5:信頼を得るための専門家との連携
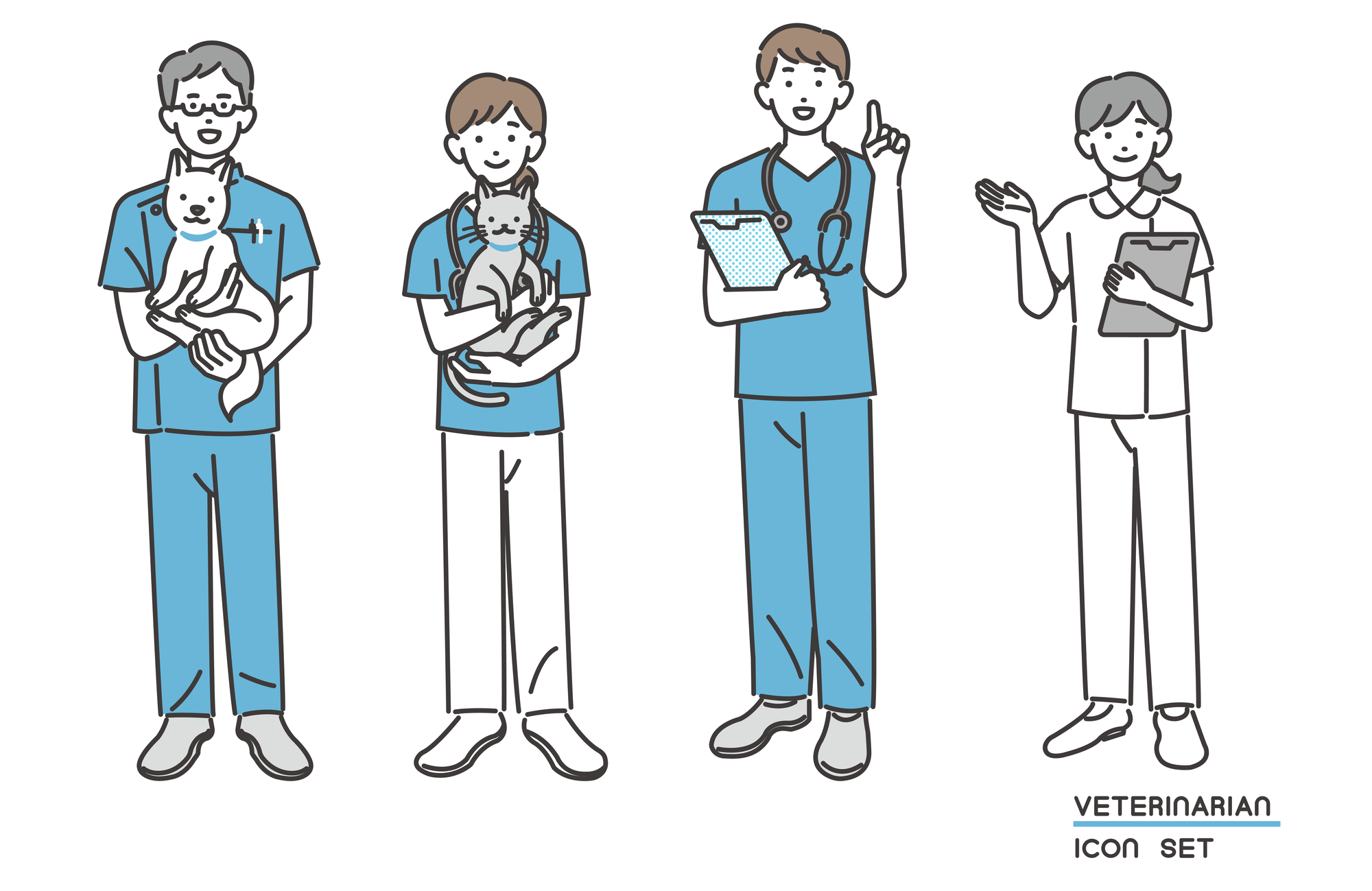
ペット事業では、専門家の存在が消費者の信頼を得るうえで重要な役割を果たします。
「獣医師監修」「ドッグトレーナー監修」「ペットトリマー監修」といった表記があるだけで、商品やサービスの説得力は格段に上がります。
さらに、以下のような効果も期待できます。
- 成分や仕様に関する科学的な妥当性の確認
- プロの視点で見た際の安心感や実用性の担保
- SNSやメディアでも紹介されやすくなる
専門家と連携する際は、「名前を貸してもらう」だけでなく、しっかりと実際の監修内容や関与度を開示することが信頼構築につながります。
立ち上げ時に避けたい“5つの落とし穴”と対策

最後に、ペット事業の立ち上げ時によく見られる「失敗パターン」と、その回避方法をご紹介します。
1. 市場ニーズの誤解
→「自分が欲しいもの」=「みんなが欲しい」とは限りません。SNSでのリサーチやクラウドファンディングなどでニーズ検証をしましょう。
2. ブランドコンセプトの曖昧さ
→コンセプトがあいまいだと、情報発信やパッケージもぶれがちに。最初にブランドピラミッドを設計することが効果的です。
3. 差別化不足による競合負け
→競合の多い領域では「独自の価値提案(USP)」が不可欠です。素材やデザイン、監修者などに“理由”を持たせましょう。
4. 宣伝不足・広報戦略の甘さ
→どんなに良い商品でも、知ってもらえなければ売れません。SNS運用、インフルエンサー活用、SEO対策など広報の手段を複合的に検討しましょう。
5. 顧客接点の継続性の欠如
→購入後のフォローがないと、リピーターにはつながりません。LINEやメルマガ、アンケートによる継続接点設計が、LTV(顧客生涯価値)を高めるカギです。
「感覚」だけでなく、戦略と信頼で勝つペットビジネスを
ペット事業は、単なる「かわいい」や「好き」という感覚だけでは継続的に成り立たせることは困難です。ターゲットの設定、市場の理解、信頼を得るための設計、そして専門家との連携という要素を、事業の初期段階からしっかりと押さえておくことがとても重要です。
ユーザー目線と専門性のバランスを保ち、感情と論理の両方に訴えかける商品戦略が成功のカギとなるでしょう。
ペット商品に信頼感を与える
獣医師監修サービスを提供しています
ペット商品に信頼感を与える
獣医師監修サービスを
行なっております