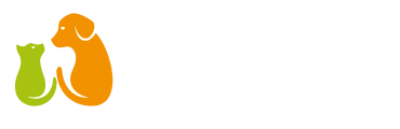ペットマーケティングは飼い主マーケティング

ペットビジネス支援をしていると、ペット業界の企業だけでなく、異業種の企業からも「ペットをターゲットにしたビジネスを始めたい」というご相談をいただくことが増えてきました。
その際に必ずお伝えするのが、「ペットマーケティング」という視点の重要性です。ただし、ここで言うペットマーケティングとは、単にペットに向けた商品やサービスのことではありません。
実際に購入を決定するのは“飼い主”であり、真にアプローチすべきは「飼い主の心理」であるということを理解する必要があります。
本記事では、飼い主の視点からペット商品・サービスを考える「飼い主マーケティング」の基本と、その具体的な手法について解説します。
飼い主が本当に求めているものとは?

結論から言えば、ペット用品の購入において飼い主が求めているのは、単なる「機能の良さ」だけではありません。 もちろん、安全性や効果、使いやすさなどの機能的価値は大切ですが、それ以上に重視されているのは“感情的価値”です。
具体的には、
- 自分の選んだものが「ペットにとって最善である」と信じられること
- 購入を通して「良い飼い主でいたい」という自己肯定感を満たせること
- 大切な家族であるペットに「愛情を注いでいる」と実感できること
つまり、ペット向け商品であっても、実際には“飼い主自身の感情や価値観”にフィットしているかどうかが購入の決め手になります。
このような視点に立つことで、ペットマーケティングは「ペットのためのマーケティング」ではなく、「飼い主のためのマーケティング」であることが明確になります。
実例:「うちの商品は機能が良い」という落とし穴

実際にあった事例をご紹介しましょう。ある家電メーカーから、「空気清浄機をペットのいる家庭向けに販売したい」というご相談を受けたことがありました。その際に提示された訴求ポイントは、「何%の嫌な匂いを除去」「独自の◯◯機能搭載」といった、機能性を強調するものでした。
確かにメーカーとしては、技術の高さや他社製品との差別化をアピールしたくなるのは当然です。しかし、ここに落とし穴があります。
飼い主がその“機能の違い”を理解し、購入の決定要因にできるかというと、それは極めて限定的です。専門的な知識がある一部の層を除けば、多くの飼い主にとっては、その機能がどれほどすごいかを具体的に理解するのは難しいのです。
むしろ、飼い主が求めているのは「この空気清浄機を使うことで、ペットが快適に過ごせる」「自分自身も安心して生活できる」といった、感情に訴える価値。その商品がペットとの暮らしにどう役立つか、自分の日常がどう豊かになるかといった“共感ポイント”がなければ、機能の優位性だけでは購入にはつながりにくいのです。
飼い主の共感を得るマーケティング設計

では、実際にどのようなマーケティング手法が効果的なのでしょうか?
1.感情に訴えるメッセージ設計
飼い主が商品を選ぶ際、「健康に長生きしてほしい」「快適に過ごしてほしい」といった思いが根底にあります。そうした気持ちに共鳴するようなメッセージを設計することで、商品やブランドに共感が生まれます。 例:「毎日をもっと元気に過ごしてほしいから、○○は素材にこだわりました」
2.飼い主自身が使いやすい設計
どれだけ優れた商品でも、使いづらければ継続的に選ばれません。パッケージの開けやすさ、収納のしやすさ、与え方の簡便さなど、飼い主目線の使い勝手もマーケティングにおいて重要です。
3.商品選びの“正当性”を支える情報提供
飼い主は「この選択でいいのか」という不安を持っています。そのため、開発背景、使用成分、第三者の評価などの情報を分かりやすく提示することが、購入の後押しになります。
4.「家族」としての価値観を尊重する
現代の飼い主の多くは、ペットを「子ども」「パートナー」などの存在として位置付けています。従来の「所有物としてのペット」という前提ではなく、「共に暮らす存在」としての価値観を尊重した訴求が求められます。
5.ライフスタイルに合った提案を行う
近年では、ペットと共にキャンプや旅行を楽しむ人が増えたり、テレワークによって日中もペットと一緒に過ごす時間が増えるなど、飼い主のライフスタイルは多様化しています。マーケティングの際には、こうした生活背景に合った提案を行うことで、より深い共感を得ることができます。
6.口コミやSNSを活用した「共感の輪」づくり
ペット関連の商品・サービスは、SNS上での体験シェアや口コミが購入の決め手になるケースが多く見られます。実際のユーザーの声や写真、動画を活用しながら、他の飼い主にも“共感される”仕掛けをつくることが、自然な信頼と認知の拡大につながります。
失敗しないための視点:自己満足型企画の落とし穴

ここで注意したいのが、「自分が良いと思うもの=売れる」という思い込みです。 企画担当者や企業側が“良い”と思うだけでは、市場では通用しないケースも少なくありません。
よくある例としては:
- 高級素材を使ったが、価格が高すぎて手が出ない
- デザイン性にこだわりすぎて、実用性に欠ける
- 機能が多すぎて、シンプルさに欠けている
このようなズレは、「飼い主のリアルな日常」に寄り添っていないことが原因です。したがって、企画段階から飼い主の声を取り入れ、リアルな悩みや使い方を把握したうえで商品やサービスを設計することが重要です。
また、マーケティング施策を行う際にも、「なぜこの施策を打つのか」「誰に何を届けたいのか」という目的の明確化が欠かせません。施策先行型のプロモーションでは、一過性の反応は得られても中長期的な信頼やリピートにはつながりません。
飼い主の声に耳を傾け、共感を得るブランドづくりを ペットマーケティングの本質は、飼い主の心理にどれだけ深く寄り添えるかにあります。
選ばれるブランドや商品は、「品質が良いから」だけでなく、「この商品を選ぶ自分が好き」「このブランドに共感できる」といった、感情的な納得感を提供できているかどうかがカギになります。
「ペットは家族」という気持ちに寄り添う
マーケティングにおける“共感”は、単にキャッチコピーやビジュアルで作り出せるものではなく、企業の理念や行動、顧客との関係性からにじみ出てくるものです。だからこそ、飼い主が「自分たちのことを理解してくれている」と感じられるような、誠実な姿勢とコミュニケーションが重要になります。
「ペットは大切な家族」とは言われ尽くした言葉でもありますが、商品を提供する企業側として大切なのは、この思いに“寄り添っているかどうか”を常に確認すること。それが「この商品を選んで良かった」と思える体験を提供することにつながるのです。
ペット商品に信頼感を与える
獣医師監修サービスを提供しています
ペット商品に信頼感を与える
獣医師監修サービスを
行なっております