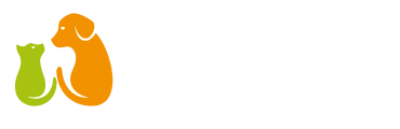売れるペット商品はこう作る!商品開発5つの視点

ペット市場の成長が続く中、新たに商品開発に取り組む企業やブランドが増えています。しかし、「かわいい」「便利」だけでは売れないのが現実。飼い主のニーズは高度化し、競争も激化するなかで、どうすれば“選ばれる商品”をつくれるのでしょうか?
本記事では、ペット業界で商品開発を担当する方や経営者に向けて、実践的な商品開発の視点を5つに整理してお届けします。ペット製品開発の現場でありがちな課題や、売れる商品に共通する考え方も紹介します。
顧客ニーズを読み解く市場調査の進め方

商品開発の第一歩は「誰の、どんな課題を解決するのか」を明確にすることです。ペットと一口に言っても、犬・猫・小動物・爬虫類など種類は多様。さらに、飼い主の年齢層や生活スタイル、飼育歴などによって求められる機能やデザインも異なります。
市場調査を行う際には、以下のような手法が有効です。
- SNSでの口コミや投稿からニーズを読み取る
- Amazonや楽天などのレビューを分析する
- 動物病院やペットショップでのヒアリング
- クラウドファンディングで事前検証する
また、同業他社のリリース情報、業界ニュース、展示会レポートなどからもヒントが得られます。ニーズを把握するだけでなく、それにどう応えるかという視点も忘れずに持ちましょう。
特に、「高齢犬向けグッズ」「アレルギー対応おやつ」など細分化されたジャンルほど、新規参入の余地があります。市場のニッチを見極めて、そこに刺さる提案をすることで、競合との差別化が図れます。
商品の“切り口”で差別化をはかる

同じカテゴリーの商品が並ぶ中で、ユーザーに「これは違う」と感じてもらうには“切り口”が重要です。多くのユーザーが似たような商品に埋もれてしまい、本当に価値のあるものが伝わりにくい時代だからこそ、切り口の設計が明暗を分けます。
例えば、
- 利用シーン(例:旅行用、介護用、夏限定)
- 素材のこだわり(例:国産、オーガニック、抗菌仕様)
- 機能性(例:噛み癖防止、誤飲防止)
また、ペット商品の特徴的な点としては、【感情面に訴える設計】がマストであるという部分。「うちの子専用」という気持ちに応えるパーソナライズ性や、「家族として扱う」ことを前提としたストーリーブランディングなどが支持される傾向にあります。
競合調査を行った上で、あえてニッチに絞る戦略も有効です。多くの人に売るよりも、“刺さる少数”に届ける方が効果的な場合もあるのです。
安全性と専門性で信頼を獲得する

ペット商品は“命に関わる”アイテムです。特に食べ物やヘルスケア用品などは、飼い主が慎重に選びます。そのため、「安心して使えるか」が購入の大きな判断基準になります。
以下のような観点で「信頼を得る一工夫」をしましょう。
- 成分や仕様の明確な表示
- 第三者機関の検査・認証を取得する
- 専門家(獣医師、ドッグトレーナーなど)の監修を受ける
また、ブランドとしての一貫性やポリシーも信頼の裏付けになります。たとえば「すべての製品に厳格な成分管理を適用している」「獣医師と連携した開発を義務付けている」など、開発体制そのものが差別化要因になります。
こうした取り組みは、商品そのものの品質向上だけでなく、プロモーションでも強力な訴求材料になります。安心・安全という信頼は、価格よりも強い購買動機になることもあります。
ペルソナ設計とプロトタイピングで検証する
「良いと思ったけれど売れなかった」原因の多くは、企画時点でのユーザー理解の甘さです。商品開発では、想定顧客=ペルソナを具体的に描くことが大切です。
- 年齢、性別、家族構成、居住地域
- ペットの種類や年齢、健康状態
- 購入理由やこだわりポイント
さらに、ペルソナの“生活背景”を深掘りすることも重要です。「平日は忙しい共働き家庭」「高齢で体力に不安のある飼い主」など、生活導線や価値観を反映した設計が求められます。
これらを明確にしたうえで、少量試作+テスト販売で市場の反応を検証すると、改良ポイントが見えてきます。最近では、クラウドファンディングを活用した市場テストもよく見かける施策の一つ。支援コメントや応援購入の動きから、リアルなニーズを把握することができます。
開発メンバーの連携と社内体制の整備
商品開発は、マーケティング、デザイン、物流など複数部門が関わるプロジェクトです。意思統一がされていないと、「企画意図と違うパッケージ」「ターゲットに届かない販促」などのズレが起きてしまいます。
- 定期的なチームミーティング
- 商品開発の目的や背景を全員で共有
- テスト販売結果を社内全体でフィードバック
などが必須となってきますが、その際に重要なのは、単なる情報共有やツールの導入だけではありません。
開発に携わるすべてのメンバーが、「誰のために」「どんな思いで」この商品をつくっているのかという“ストーリー”を共有し、共通認識として持つことです。
たとえば、開発者と営業チーム、カスタマーサポートが、それぞれ別のターゲット像を描いていたり、製品に込めた価値観を正確に理解できていなければ、顧客との接点にブレが生じます。その結果、せっかくの商品が「伝わらない」リスクも。
「この商品はなぜ生まれたのか」「どんな飼い主とペットの毎日を支えたいのか」。そういった背景や想いを、チーム内で何度でもすり合わせ、ブレたときには徹底的に対話を重ねる。そのような定性的な連携こそが、顧客に響く一貫性ある商品づくりにつながるのです。
開発スピードだけでなく、“解像度の高い共通理解”を持つことが、選ばれるペット商品を生む土壌となるでしょう。
感覚ではなく戦略でつくる、選ばれるペット商品
「なんとなくかわいいから」「トレンドだから」といった感覚だけでは、今のペット市場では通用しません。ペット商品開発の現場では、顧客理解・差別化視点・信頼構築・組織連携といった複合的な戦略が必要です。
また、商品開発は「売ること」だけが目的ではありません。ブランドの世界観を伝え、顧客との関係性を深め、長期的な信頼と支持を得るための接点でもあります。
特に、開発・販売に関わるすべてのメンバーが、ターゲットや商品に込めた思いをどれだけ深く理解し、共有しているかは、最終的な商品力に直結します。社内でブレが生じたときに立ち止まり、対話を重ねながら想いをすり合わせていく姿勢が、一貫性のある商品づくりには欠かせません。
着実なリサーチと検証を重ねて、「本当に飼い主とペットに寄り添った商品」を届けていきましょう。その積み重ねが、ブランド価値を高め、選ばれ続ける理由になっていくはずです。
ペット商品に信頼感を与える
獣医師監修サービスを提供しています
ペット商品に信頼感を与える
獣医師監修サービスを
行なっております