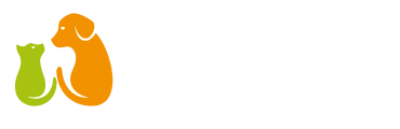“商品+α”の提案がカギ!選ばれるペット向けソリューションの作り方

ペット市場が拡大を続ける中、消費者(ペット飼い主)の選択基準も年々シビアになっています。単に「良い商品をつくれば売れる」という時代は過ぎ去り、いまや飼い主たちは“モノ”ではなく“体験”や“価値観”にお金を払うようになっています。
そんな中で注目を集めているのが、ソリューション型のペットビジネス。つまり、「商品+α」で飼い主とペットの暮らし全体を支える視点です。
本記事では、ペット業界で商品企画・事業企画を担う担当者・経営層に向けて、選ばれるソリューション設計のポイントをお伝えしていきます。
いま、なぜ「ソリューション型」が求められているのか?

ペットは「家族の一員」という価値観がすでにあたりまえのこととして一般化しており、それに伴ってニーズはより深く、個別化しています。
- 健康管理をもっとしっかりしたい
- 飼育に不安がある初心者へのサポートがほしい
- ライフスタイルに合ったケア用品を選びたい
こうしたニーズに対し、商品単体だけでは応えきれないケースが増えています。たとえば「シニア犬向けの関節サポートサプリ」だけでは不十分で、それをどう使い続けるか、どう状態をチェックするかまで寄り添う仕組みが求められています。
このように、「商品+サービス」=ソリューションという設計が、飼い主との継続的な信頼関係を築くカギとなってきているのです。
ソリューション型の事例に学ぶ、成功のパターン
では、実際にソリューションとして機能している商品・サービスにはどんなものがあるのでしょうか?
事例1:フード×定期配送+獣医師チャット相談
Amazonでは、獣医師がお客様の相談内容をもとにペットフードを紹介する「獣医師フード相談」を無料で提供しています。このように、購入前後の疑問や不安に専門家が寄り添う仕組みが、選ばれる理由となっているのです。
事例2:見守りカメラ×アプリ通知+行動サポート
Furbo(ファーボ)ドッグカメラは、ペットの行動を360°で見守れるカメラに加え、スマートフォンアプリと連携し、吠えたときの通知や自動録画、双方向の会話機能、さらには行動記録の分析まで可能なサブスクリプションサービスを展開しています。
これは単なる「カメラ」ではなく、「離れていても飼い主がそばにいる感覚を届ける」という体験価値そのもの。商品+アプリ+継続的なデータ提供という仕組みが、信頼・安心・利便性を総合的に提供しています。
事例3:ケア用品×ライフステージ診断コンテンツ
ペット用歯ブラシや歯磨きジェルを販売しているライオンでは、獣医師による犬の歯磨きのやり方を解説した動画を自社WEBページで展開しています。商品の使い方を正しく理解し、飼い主が自信を持ってケアできるようサポートすることで、継続利用と信頼の獲得につなげています。
顧客体験をデザインするという視点

ソリューション型の商品設計では、顧客がどんな気持ちで購入し、どんな期待や不安を持ちながら使い続けるのかを想像することが重要です。
顧客体験設計の出発点としては、以下のような問いが役立ちます。
- 初めて購入する人は、何に迷うか?
- 使い方に失敗するとどんなリスクがあるか?
- 買ったあとに誰に相談できる仕組みがあるか?
- どんな時に「また買おう」と感じるか?
このような視点から、
- サポートコンテンツ(FAQ・動画・チュートリアル)
- ユーザー参加型のキャンペーンやフォーラム
- 飼い主の感情に寄り添うデザインやコピー
などを組み込むことで、「安心して買って、安心して使える」体験が設計されます。結果的に、顧客の満足度やブランド信頼度も高まります。
継続利用につなげる仕組みとLTV最大化
単発購入ではなく、「また選んでもらう」仕組みづくりがペットビジネスの成長には欠かせません。ここで重要になるのが、LTV(顧客生涯価値)の最大化です。
以下のような設計がLTV向上に貢献します。
- 定期便モデル+カスタマイズ選択肢(例:体重変化に応じて内容変更)
- LINEやアプリでのリマインド通知、使用ログ機能
- リピート時の特典やフィードバック施策(例:レビュー投稿で割引)
これらはすべて「顧客が継続しやすい仕組み」であり、製品そのものの満足度と同じくらい大切です。また、獣医師や専門家のコメントを定期的に配信することで、“次もここで買いたい”という信頼の蓄積にもつながります。
よくある課題とその乗り越え方
ソリューション型ビジネスはメリットが多い一方で、設計や運用における課題もあります。以下はよくあるつまずきポイントです。
課題1:導入コストが高い
動画制作やシステム開発など、初期コストが大きくなりがち。最初は簡易な仕組みから始めて、ユーザー反応を見ながら段階的に拡張する方法がおすすめです。
課題2:ターゲット像が曖昧
誰にどのような体験を提供したいのかが明確でないと、体験がぼやけてしまいます。ペルソナ設計とユーザーインタビューなどを通じて、“リアルな困りごと”に着目することが大切です。
課題3:社内での価値共有が不足
「なぜこの仕組みが必要なのか」を開発チームや販売担当が正しく理解していないと、導入後の運用が形骸化します。背景にあるストーリーや提供価値を、社内全体で共有する仕組みづくりが成功の鍵になります。
モノを売るのではなく、関係性をつくる
ペットビジネスにおけるソリューション型の展開は、単なる“付加価値”ではなく、“本質的な価値提供”そのものです。商品を届けたあとに「どうだったか」「その後どうなったか」にまで責任を持つ姿勢が、現代の飼い主からの信頼を集める要因になります。
そして何よりも、チーム全体が「この商品は誰のどんな暮らしを支えたいのか」という思いを共有し、ブレたらすぐに話し合う文化を育てることが、ソリューション型ビジネスの根幹を支える力になります。
プロダクトからプロセスへ。商品から体験へ。そんな視点をもって、選ばれるブランドづくりにチャレンジしていきましょう。
ペット商品に信頼感を与える
獣医師監修サービスを提供しています
ペット商品に信頼感を与える
獣医師監修サービスを
行なっております